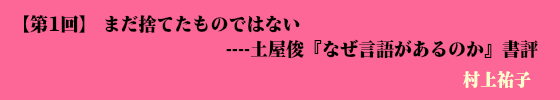
★はじめに
フレーゲ研究から言語行為論に踏み込んだ著者が、言語の仕組み探求という問題設定は無意味であり「言語はなぜ存在するのか」という問いこそが哲学的に有意義であると論じ、「言語は文脈を補完する」テーゼを主張するに至る哲学的分析そのものはきわめてオーソドックスな哲学の書法によるものだが、その一方で、本書21章のタイトル「日本における分析哲学の現状、終焉あるいは将来」に象徴されるように、この本を哲学そのもの、とくに日本の哲学研究への期待と絶望の両極を揺れ動く記録と読むこともできる。
★自己再生する哲学
本書の序章で分析哲学の終わりは高らかに宣言される。哲学を「科学の揺籃」と位置付け、「哲学が終わることは、その哲学にとっては誇りとすべきことなのである」とする著者の分析は正しい。ただし哲学にはもう一つの重要な側面があることを、著者はもっと強調してもよかった。それは技術開発を契機とする科学的手法の変化と、またそれによって得られた新たな科学的知見が既存哲学の前提を揺るがしたとき、問題となった前提を修正したうえで哲学体系を再構築する営みとしての哲学、つまり自己再生する哲学の可能性である。この意味で、言語学・認知科学の知見を取り入れて情報伝達に関する哲学理論を再構築することは、その素材となる哲学理論の選択を含めて、今後の課題となるだろう。とくにこの4巻で取り上げられている言語に関する主張は、著者が1980年代から関わってきた状況意味論での言語観、すなわち各発話の意味はその発話が生じた状況に依存するといった文脈主義を踏み越えて、情報・意味を伝達するのは状況そのものであるという考え方に基づく。つまり、状況を補填する情報伝達手段として発話を考えるべきであるという著者の主張は状況意味論の路線を発展させたものであることが明らかである。
著者はこの課題を「科学的思考と哲学的思考を対立させて考えるという発想は本質的に拒否されることになる」と一般化して関わり続けようとしている。その一環が、この著作集の他巻所収の電子図書館・オープンアクセスといった場面に見られるICT技術開発とそれにまつわる社会制度が学術研究へ与える影響の分析である。その活動は、迂遠といわれるかもしれないが、現在の技術発展・社会変化に伴う哲学の再構築につながる考察と位置付けられよう。
★哲学と哲学史
また分析哲学の終焉を宣告するなら、哲学と哲学史の区別を明確にすべきであった。著者の指摘通り、日本に限らず分析哲学、とくに言語哲学が終わったとしても、ここしばらく初期分析哲学が哲学史の一分野として興隆してきたように、分析哲学を歴史的に位置付ける作業はまだ始まったばかりといえる。これまでのタイプの日本の哲学によくみられるような、歴史的哲学者の著作を緻密に読み解くことで個別の哲学的問題に自分なりの解答を与えるという方向性での分析哲学研究は、哲学史研究として有意義な営みとなるはずであり、この手法では日本は国際的に先行しているとすらみなせる。つまり、日本の哲学には現状でもまだ希望がある、と著者に反論したい。
★哲学者と哲学教師
一方で、哲学者と哲学教師を区別してみると、著者の絶望が幾分は救われるかもしれない。科学技術・社会システム等広範な場面への哲学の寄与が注目されるなか、個別科学の研究者・技術者が哲学を勉強すべきだと主張するのは、哲学者なら怠慢、哲学教師なら奢りだ。むしろ哲学者が個別科学の現場、また人間の営みの現場に飛び込んで、チームの一員として問題に取り組むべきなのだ。たしかに教育に深くかかわっている場合はこのような(狭義の)「哲学以外の活動」に時間を大きく割くのは難しいだろう。しかし、哲学者は現在日本で通常考えられている意味での哲学研究とは異なる場面で求められている。哲学者に問題解決が要請されているとすれば、哲学者の行うべきことは過去の哲学文献へ注釈を施すことではなくなる。もちろん既存の文献を書かれた時代の問題への解決案として参照し、歴史的に評価することは必要だが、それは問題解決の手段にすぎない。むしろより本質的な営みは、哲学者の視点での現状分析と将来予測、とくに現実をめぐる議論の論理的陥穽の指摘・修正である。この点は現在の日本における哲学教育の面でも強調されてしかるべきであろう。
この文脈で、「土屋俊は哲学をやっていない(あるいはやめた)」という一部の評価を改めて眺めると、たしかに最近の土屋俊は古典的意味での哲学教師、あるいは哲学史研究はやめている。しかし著者自身の哲学の位置付けは以下のように述べられている。
本書230-232ページ
哲学はなぜ難しいのか。それは、考えるということが難しいからであり、この難しいことをやり続けよと要求するのが哲学だからである。【中略】「考え続ける」ということが、人間にとっていかに異常なことであるかということである。【中略】その結果は、哲学の亜種として、ふたつのものを生み出した。ひとつは、「思想としての哲学」であり、もうひとつは「理論としての哲学」である。「思想」とは、どこかでそれ以上考えることをやめた哲学のことである。【中略】哲学的「理論」というものは、【中略】考える手間をある程度軽減するために考えられたものである。
定まった思想はないかもしれない。哲学理論は提示していないかもしれない。しかし、考え続ける哲学者としての土屋俊は活動の場を今なお広げている。

村上祐子(むらかみゆうこ) 東北大学
東北大学理学研究科准教授。東京大学大学院単位取得退学、インディアナ大学でPh.D.取得。日本学術振興会特別研究員、国立情報学研究所特任助教授を経て現職。
