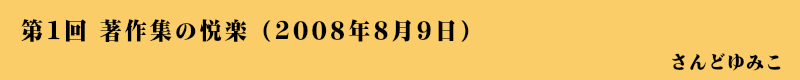
・・・8月9日・・
最悪に暑い昨日、国会図書館に土屋俊コレクションに入れる雑誌論文のコピーをとりに行った。夏休みのせいか、いつもより混んでいるが、周囲の大木ではジージーと蝉が啼き、青い空にぽっかりと浮く最高裁の石棺のような建物を見ていると、なぜか人類の無常を感じてしまうのだ。
著作目録から収録論文を画定して全6巻にしたはずだが、ぽろぽろ漏れた論文が出てくる。例によってそれらは数点入手できたが、昨日の最大の収穫は「戦後日本における心身問題の帰結」(第2巻 心の科学の可能性、所収)という論文だ。
心身問題といってもうつ病や心身症の話ではない。心と体の2元論がもとにあって、体がどこにあるのかは明白だが、では心がどこにあるのかという話になったとき、哲学者に専ら任された問題らしい。
これは目録には文芸春秋別冊とあったがヨウとして行方が知れず、途中で土屋氏が
>あれっ、いつのまに『文藝春秋』になってしまったのでしょうか。これは河出書房の『文藝』の別冊です。
と言い出し、それでも見つからない曲者だったのだ。数日前のメールで
>つまり、別冊文藝ではあったのですが、出版上は「図書」の扱いになっていたということだと思います。証拠を添付します。
と変更になり、ようやく和書の検索で見つけることができた。
目次をみると、22年前の雑誌(単行本扱いで出版)でタイトルは「現代思想の饗宴」、中沢新一、上野千鶴子、竹田青嗣、橋爪大三郎、など現在も活躍する有名人が並んでいる。
有名人は1日にしてならず・・・、学術の世界はそれが厳しいところなのかもしれない。当時若かった上野氏が『お一人様の老後』で大ベストセラーを当てるなどと誰が予想したであろうか。
それにしても、ほかの有名人とは違い、土屋氏はずいぶん気の毒だ。なぜなら、わたしのようないい加減な編集者がついていて、
>「心身問題」は今回はあきらめましょう。国会図書館で目次をコピーしましたが、論文はありませんでした。そこに書いている人達もちょっと違う分野の人たちでした。
などと、すぐにあきらめてしまうのに妥協せず、ついに自ら、論文の在りかを突きとめたくらいなのだ。
誤解がないようお願いしたいのだが、くろしお出版の編集者がみなわたしのようにいい加減だということではない。わたしはあまりにアバウトなので、編集部には今でも半分出入り禁止状態なのです・・・。
まあ、とにかく、これらの人々と共に「文藝」に書いていた気鋭の哲学者がなぜ、(言語学では地歩を築いているとはいえ)、哲学や図書館学では実績のないくろしおで著作集をだすのだろうか?そういえば、かの岩波書店ではことし、哲学界の総力を結集した岩波講座「哲学」を刊行中で、土屋氏のお仲間も多数編集や執筆に加わっているはずだ。
土屋氏は今回、加わっているのだろうか?過去の講座には数点魅力的な論文を載せていて、コレクションへの収録許諾も先方からすみやかに、いただいたはずだが・・・。
・・・8月30日・・・
いま、土屋コレクションは本文の編集作業を中断して、パンフレット作りに集中している。前回コラムの私の疑問に、土屋氏はメールで答えてくださった。(土屋氏は今回は参加していないとのこと。)
ぼく自身は、いわゆる哲学らしい哲学は80年代でかなり自覚的にほとんどやめてしまっています(90年代の約束論は、いわゆる哲学らしい哲学とは考えていませんでした。まあ、読み直してみると、ひどく哲学くさいわけですが)。それよりも本当の哲学的思考は、個別科学、現実問題の中で活かさないといけないと考えるようになった(その考え方は、4巻に収録の「科学と哲学の正しい関係」に解説してあります)ので、結局、80年代以降は、(ちょっと哲学っぽい認知科学基礎論はやっていましたが)、基本的には状況意味論、ヒューマンインターフェイス、ネットワーク、音声対話(コーパス製作と分析)、情報倫理と、そして、図書館情報学と、まあ、コンピュータ・情報科学まわりといえばそうなのですが、一応個別科学をやってきて、どの分野でも科研費ぐらいはとれる成果は出してきました(この成果はほとんど今回の著作集にははいっていません)。よくもまあいろいろなことをやってきたものだと思います。あえていえば、状況意味論は多分、最初に本家のスタンフォードに行った一人だと思いますし、「情報はだれのものかーー知識への権利」は情報倫理の最初の日本語の論文ですし、千葉大学の地図対話コーパスは日本で最初のちゃんとしたコーパスです(多分、品質的には今でもいちばんいいはずです)し、図書館情報学では、どうも一番引用される著者のようですから、哲学者としてはよくやっているのだろうと思いますが、哲学っぽい論文がますます減っているので、哲学のメインストリームとしては扱いにくいということになるのだと思います。・・・
これはかなり率直かつ、簡潔で、いきいきと自分を語っているように思われるので、著者の許可を得て、掲載させていただいた。このように誠実なお人柄の大学者であるとわたしは思うのだが、どうもときどき、わたしはなにか言ってしまいたくなるのだ。
たとえば、何故著作集か?という問いに出版社サイドから答えると、いろいろな答え方ができる。一つには語学系出版社の社長の心に兆した、ささやかな虚栄心かもしれない。土屋氏は現在の日本の哲学の、メインストリームではないかもしれないが、すくなくとも、言語という、20世紀後半の人文学では常に語られる領域の研究から出発して、いちはやく情報化社会の問題に立ち向かい、さらに学術情報の流通とその将来という、当社にとっても他人事ではないテーマに取り組んでいる。土屋氏は人文学の王道をいく学者であり、私の虚栄心をくすぐると同時に危険な著者でもある。
今回、コレクションの編集の一番初めの段階で、土屋氏はご自分の所有するいわゆる著者最終原稿のデータを探し出すことに執念を燃やされた。土屋氏のような大学者ともなると所有する電子ファイルは膨大なのだ。しかしながら、過去30年の哲学的営為が著作集にまとめられていく過程において、著者、出版社のうち、どちらがファイルを提供したか、という問題はかなり、後方に拡散してしまったように思われる。もちろん、これからそういう問題がふたたび、クローズアップされることは大いにありえる。最終的に土屋氏は(今すぐにではないが)、ご自分のお書きになったものは自身のホームページで公開されるだろう。しかし、これは当社にはかかわりのないことなのだ。
8月31日
ここでまた、最初の問いに帰ってくることになる。何故、著作集なのか?
デジタル技術の進展でこれからは人の一生、誕生から、初めて歩いた日の動画像、入学式、書いた絵のすべて、かいた文章のすべて、記録した写真も動画もすべて、金婚式の様子まで、親指の先ほどのマイクロチップに全部入ってしまうのだ。そういう時代なら一人の学者の学位論文から、仲間と作ったテキスト、単著あるいは共著論文、著作物のすべてが彼または彼女の所属する機関リポジトリに登録され、著者の自宅のパソコンにも保管される。いま、学位論文を書いているような人が50代を超えて大学者となり、著作集を編むというときはどういうやりかたになるのだろう???、そもそも、機関リポジトリは長くつづくものなのか??それは図書館が収集から発信へとベクトルを変えたものだという。われわれ出版社はウェブで論文を見て興味をそそられ、著者と連絡をとり、もっと全体像を知りたいと思う場合もあれば、ある程度読んでしまったので、もう充分、と思ってしまう場合もあるだろう。
リポジトリと大学出版会はやがて統合されるかもしれないが、かなりな大所帯となる組織で採算をとるのは大変だろうな・・・。
まあ、我々も当分はやり慣れた出版という業態で過ごしていけそうではある。そして、著作集の編集というのはなかなか楽しい経験だ。過去に向き合うということは膨大なエネルギーを要する、と土屋氏は書いている。
過去に自分が書いた文章を読み直すことは勇気がいることであるが、たとえば、すでに過ぎてしまった近未来を予測していて、それが的中したことを知るとすこしほっとする。この変化の著しい現代に過去の論考を集めた「著作集」でもあるまいという印象を否定はしないし、また、学術的成果物を電子的にオープンに利用可能とすることの意義は誰よりも理解しているつもりであるが、通読に堪える自選アンソロジーを編むという作業は物理的、心理的に膨大なものであり、編集者、出版者の協力なしには不可能であることを実感し、現代日本の出版流通の状況を受け入れて印刷物とする形態を選択した。(著者刊行の言葉より)
30年後に大学者が著作集を編むときもその人は過去を振り返ることになる。過去に向き合うことは学者の仕事においても必要であり、著作集というきっかけがなくても、みな何らかの方法でしているのではないか。また、30年後、もし万一、紙の本という形態、その流通がなくなっているとしても、たった一人で過去を振り返ることは単なる回顧であまり意味がないように思える。いや、ウェブで流していれば、やがて「読者の広場」のようなサイトが形成されるのかもしれない。そのようなサイトの中で「ともに編集する人」、がでてくれば今の編集者のような役割をはたすかもしれないが・・・。
過去の仕事が現在、未来に開かれるためには、内容についてあれこれうるさいことをいう人々、賞賛する人々、ともにその時代をすごし共感する人々、または反発する人々がいなければならず、その人たち、あるいはその人たちの属する学術コミュニテイーに、書いたものをとどけなければ意味がない。
ということで、土屋氏が「現代日本の出版流通の状況を受け入れて印刷物とする形態」を選択されたのが正しかった、と思っていただけるよう、これからも、遺漏なく、やっていきたい。
