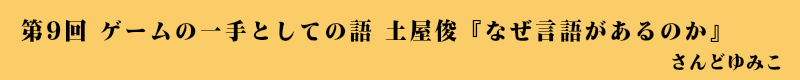
ゲームの一手としての語 土屋俊『なぜ言語があるのか』
お盆休みを過ぎて、土屋俊言語・哲学コレクションは(3巻をジャンプして)4巻が校了となった。
今回から編集を若手に任せて私は気楽な立場からの参加である。
序章で著者は「言語哲学は終わった」と表明している。そのように哲学的問題関心が科学的探求活動へ解消することはその哲学にとって誇りとすべきことであり、それでも「哲学は科学を生み出しつづけなければ存在意義がない」、と哲学の目的について述べている。
この、4巻だけでも大部で、しかも既刊の1、2巻とも密接に関係する言語・情報・論理をめぐる著述全体についてどなたか言及してくださる方はいないのだろうか。あるいは反論は? 著者は膨大な先行著述を吟味してこれらの著述を成したのに、外部から見る限りあまり反応がないらしいのは、著者にとって気の毒なようでもあり、関連学会にとっても論争のいいチャンスを逸しているようにも思える。
当社は哲学系の出版社ではないので、ゲラを読むことは本来不可能なのかもしれない。ただ日本語で書いてあることだけをよすがに読んできたのだが、やはり現在までの言語学の方向性を批判するところへは、注意が向いてしまう。
しかし、例えば9章「ゲームの一手としての語」は初出が99年だが、そこで述べられている「文に対する語の優位性の再認識」についていえば、現在当社で刊行している言語学の専門書のうち、文を研究の対象とするものは確かに多い。けれども例えば、世界の諸言語に見られる類別詞を理論的、個別的に扱った西光義弘・水口志乃扶編『類別詞の対照』(2004)、あるいは「音声という「周辺領域」にあえて目を向けることで言語やコミュニケーション、そして文法に対する理解を深める」定延利之・中川正之編『音声文法の対照』(2007)など、さまざまなアプローチで言語とその周辺を探求しようとする研究の成果が刊行されている。
もちろん著者が言いたいのは、言語学においては生成言語学的研究の優位ということであり、哲学においても文または命題が真理値を担うということが広く認められていたことを指している。それに対し、著者の立場は、「混沌とした音声言語現象は、それ自体が完結し、自立した事実なのであり、その背後に要請されるものがあったとしても、それは単なる理論的な要請であり、記述の簡潔化のための定義にすぎない。文の組織性、体系性は、研究の結果得られた知見であり、探求の対象となる事実ではない。この区別を明確に保持することこそがこれからの言語研究にとってもっとも重要な出発点となるであろう。(9章3節)」とあるところに見てとれる。
そして著者は「言語使用のある程度の持続」を「ゲーム」という概念を持ち出すことによって、そのなかで語の位置付けを考えることになる。
なるほどそうかと、同意したくなる理屈は以下の一節で、論敵(であると著者が想定している)生成文法学派の主張を逆手にとって、「文は原理的に無限の集合であり、その要素のすべて、つまりそれぞれの文を学習することはできない。それゆえに、同じ文が繰り返し発話されるということは、それ自体が説明されるべきことであり、異なる場面では異なる文が発話されることは自然である。」と述べている。それに対し「語は有限であり、したがって、異なる場面で同じ語が発話されることこそがまた自然である。異なる場面で同じ語が発話されることによってその異なる場面同士は共有する特徴を持つことになり、これによってさまざまな場面が一つのタイプを共有することになる。このような秩序化は文によっては生じないのである。(9章4節)」
そして、その拡張線上にある「最後の一手としての言語」という立場から「言葉の意味は文脈によって決定されるのではなく、言葉の意味が文脈をおぎなうのである。」(序章)として言語の補足主義的な見方を示している。(この場合の文脈とは周囲の状況というような意味で、第1巻でも幾度か触れられている。)
このように著者の見解は普段私が親しんでいる言語の見方とはかなり異なるのだし、上に引用した中に出てくる「ゲーム、場面、タイプ」などという言葉も、情報や言語に関する実在論的理解とのことであるが、まだ十分に展開されていないことを著者も認めているようである。そのため、この巻は言語哲学が終わったという表明と言語というものへの著者の根本的観点が十分に論述されていない状況の間で刊行されるようであり、さらに著者の関心がすでに続巻へ向けて走り出しているようなので、(十分な論述が)いつなされるのかを「待つ楽しみ」があるようなのである。
