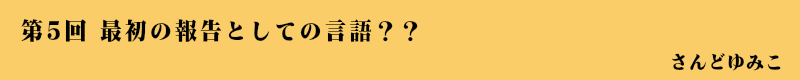
土屋俊コレクションの第1巻「真の包括的な言語の科学」が25日に発売になる。紀伊国屋書店の新宿本店や南口店ではそれぞれ15冊と、平積みにするほど、仕入れていただいた。哲学者の著作集ではあるが、「この巻は言語学の棚に入れてほしい!」というのが著者の熱い思いである。その思いとは裏腹に土屋氏の書きものは言語学の現状にいつも過激に批判的なので、どこまで受け入れてもらえるか、私としては心配である。
それに編集者を務めた私もこの巻に収めた土屋氏の論考に引っ掛かるところがないわけではない。I部の「日本語の意味論をもとめて」のように、状況意味論の日本語への適用と日本語研究から状況意味論へのフィードバック、というような専門的な研究に口をはさむことは難しい。しかし、III部の「真の包括的な言語の科学への道」におさめられたエッセイは著者の言語観を表明したものが主であるので、触発されていろいろなことを考えてしまうのである。
たとえば341ページにある1節、「言語は、一定の文脈、状況においてのみ意味を持ち得るということは、繰り返すまでもない教訓であるが、よく考えてみれば、本当に十分に文脈が整ったならば、もはやあえて言葉を口にする必要すらないはずである。したがって、言語を使用するということは、文脈を整えるという作業では十分でなかったことを補足することであるという、言語に関する非自律的な補足主義的見方をとることが可能になる。」
たしかに状況の中にメンバーがそろっている場面ではこのように補足主義的な見方をとることは可能だろう。しかし、その場にいなかった相手にその場で起こったことを報告する場合はどうだろうか。その場合、事態を報告しようとすれば、「文」の各要素はかなり不可欠のものになるはずである。
以下は編集者から著者への質問である。
先生がいわれる標記のことですが、状況の中で生起する、ということで、お膳立てを整えたうえで少しだけ加える(漸増)といいますが、言語の用途としては状況のなかにメンバーがそろっている場合のほかに、報告の場合があると思うのですが。報告の場合はかなり各要素がそろっていないと情報の内容が伝わらないような気がします。大昔男たちは狩猟をして、女たちはこどもを連れて木の実や芋を採集する。夜、家族が集まって父親に「上の子が上手に芋を掘った」「下の子が仲間にいじめられた」と伝えたくなるでしょう。伝えたい欲求は、少しだけ付け加える場合より、最初から丸ごと説明するほうが大きいと思います。子供の成長の目覚ましいある瞬間を伝えたい、そのほかにも「今日行ったエリアにはほかの群れが来ていて争いになった」「今日行った方面の氷は緩んでいて危険だった」というような生存にかかわる情報もあります。方向と距離で伝達する方法もありますが、「本当に怖かった」、「うれしかった」、など感情まで一緒に説明し、「それは大変だったね」、などの反応を引き出せるのですから、複雑に分節化された言語はとても使い勝手が良かったのではないでしょうか。
この質問に対して著者からは第4巻に収録されている論考と同じ語りくちの回答があっただけである。著者はそれよりもウェブに挙げる序文を完成させることに追われており、しかも編集者の質問は第4巻「なぜ言語があるのか?」に関することにずれ込んでいるからである。
報告の場合は「誰が」(「誰に」)「何を」「した/させた」、「誰が」(「誰から」)「何を」「した/された」など、使役、受け身の表現は明確に自律的(著者の用語(非自律的)から借用、「それ自体独立して構造を持っている」というように理解しているが誤解かも)でないと聞き手にはわからない。~しようとしたけれど「できた/できなかった」等の結果補語、ある作業が「終わった/まだやっている」などのアスペクト表現も自律的でなければ伝わらない。このように自律的な言語を使用すると、一緒にいないときの様子も詳細に再現することができるし、さらに、その時のその人たちの、怖かった、嬉しかった、大変だったなどの心的状態に共感できれば、群れ全体は共感に支えられて一体化して強くなり、他の群れに抜きんでることができる。
複雑に分節化された言語を使用しなくても、「干ばつでも芋の掘れるエリア」を他者に伝えることはできるが、他者の経験を、自律的な言語によって詳細に追体験し、いわば他者の経験を丸ごと味わうことによって生まれる共感や愛情はそうでない大雑把な追体験しかできない場合より、はるかに強いと思うのだ。
というように考えていくと言語が自律的になっていったのも、そういう言語を使う集団のほうが共感や愛情という膠で補強され、強くなれる、という道筋をたどることができるのかもしれない。
第1巻で著者が最も言語学プロパーの人に読んでもらいたいのは、第1部「日本語の意味論をもとめて」だということは、しばしば伺ったことである。残念ながら月刊言語の連載時には思ったほど反響がなくてがっかりされた旨、お書きになっており、またこの再録を再挑戦と表現している。それに比べてここで取り上げたⅢ部について、著者がどういう観点を持っているか、その詳細は第4巻を待つことになる。著者は30年前から書いていることがほとんど一貫していてあまり変化しないのが驚異的であるので、このまま自説を展開されることも予想されるが、そうでないかもしれない。いずれにせよ、第4巻が楽しみなのである。
5月からの編集作業中、私からの質問に著者がすぐに正面から答えることはなかったが、「なにか書きます」というメールを何回か受け取ることによって、著者が見当外れのことが多い編集者の質問に対しても「今は答えられないが無視してはいない」というメッセージを受け取ることができた。今回も、私は、そのように感じているのである。
